こんにちは、よつば歯科クリニックです✨
みなさん、「歯石とりのあと、冷たいものがしみる…」って感じたことありませんか❓
実は、これって多くの人が経験することなんです❗
「せっかくクリーニングしてもらったのに、なんでしみるの?」
「歯が悪くなったのかな…?」
そんな不安を感じる方も多いけど、
ほとんどの場合は一時的な反応なので安心してください✨✨
今日は、歯石とりのあとにしみる理由と、
しみたときにできるやさしい対処法を、詳しくお話します✨✨
まず「歯石」ってなに?
歯石とは、歯の表面についた歯垢(プラーク)がかたくなったもののこと!
歯みがきでは落とせなくなって、時間が経つと石のようにガチガチに固まります。
歯石の表面はデコボコしていて、そこにまた歯垢がつきやすくなるので、
そのままにしておくと歯ぐきの炎症(歯肉炎)や歯周病の原因に!
だから、定期的な「歯石とり(スケーリング)」が大切なんです✨
しみる原因①:歯石に守られていた部分が急に出てくる
ちょっと意外かもしれませんが、
歯石は“悪者”であると同時に、一時的に歯を覆って守っていた状態のこともあります。
長い間ついていた歯石を取ると、
その下の「象牙質(ぞうげしつ)」という部分が急に外の刺激にさらされることに
象牙質は、歯の神経につながる細い管がたくさん通っているので、
冷たいものや風があたると、その刺激が神経に伝わって“キーン!”としみるんです❄️
でもこれは一時的な知覚過敏で、数日〜1週間くらいで落ち着くことがほとんどです❗
しみる原因②:歯ぐきが下がって根っこが見えている
歯石がたまっていると、歯ぐきに炎症が起きて腫れたり下がったりします。
歯石をとると炎症がおさまって歯ぐきが引き締まるのですが、
そのときに根っこの部分(セメント質)が見えてくることがあります。
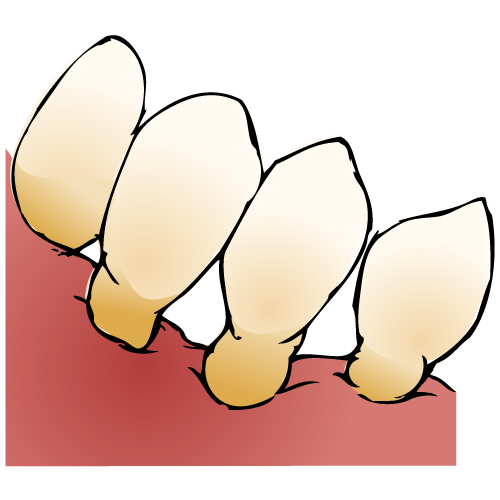
根っこの部分は、エナメル質よりもやわらかくて刺激に敏感。
冷たい水・風・歯ブラシの刺激などでもしみやすいんです。
でもこれも、歯ぐきが健康を取り戻しているサインでもあります✨
しみる原因③:お掃除中の刺激による一時的な反応
歯石とりでは「超音波スケーラー」という機械を使います。
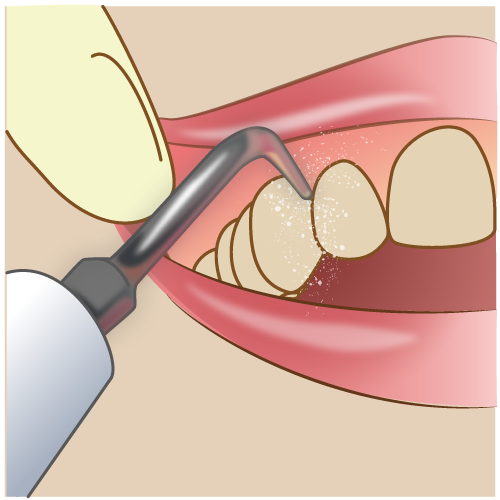
細かい振動で歯石を落としていくのですが、その振動や水流で
歯の表面や神経が一時的に敏感になることがあります。
これも数日で自然におさまるケースが多いので、
「お掃除の刺激がちょっと残ってるんだな〜」と思って大丈夫!
しみたときの対処法①:しみ止め成分入り歯みがき粉
しみるときは、歯みがき粉の選び方がとっても大事!
おすすめは
⭐️シュミテクト
⭐️システマセンシティブ
⭐️メルサージュヒスケア など
これらには「硝酸カリウム」や「乳酸アルミニウム」など、
刺激をブロックしてくれる成分が入っています
ポイントは、強くこすらずにやさしく磨くこと!
しみる部分をゴシゴシしすぎると、逆に悪化しちゃうこともあるから注意です⚠️

しみたときの対処法②:冷たい・酸っぱい・熱いを少し控える
しみるときは、歯がちょっと敏感になっている状態
そんなときに刺激の強い飲食をすると、余計にピリッと感じやすくなります。
⛔避けたいものリスト
⚠️冷たいアイスや氷水
⚠️酸っぱいレモン、酢ドリンク
⚠️熱すぎるスープやコーヒー☕️
これらを少し控えるだけで、しみる感覚が軽くなることもあります!
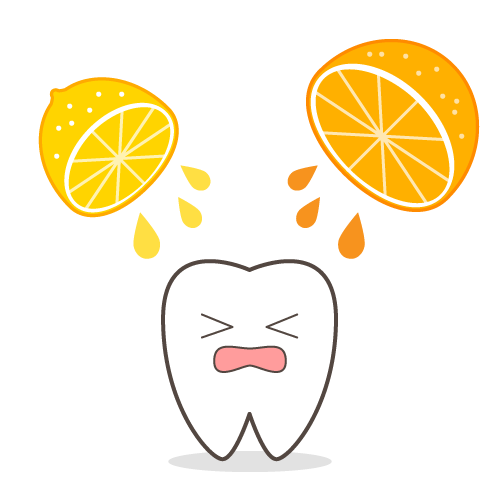
しみたときの対処法③:やさしい歯みがきと保湿ケア
しみる部分があると、つい「その歯は触らないでおこう😮💨」と思いがち。
でも、磨かないでいるとそこに歯垢がついて、もっと悪化することも
そこでおすすめは✨
⭐️やわらかめの歯ブラシ(毛先が細いタイプ)
⭐️ぬるま湯でゆすぐ(冷たい水は避ける)
⭐️口の中を乾かさないように意識すること
特に寝る前は唾液が減るので、**保湿ジェル(リカルデントやオーラルピースなど)**を使うのも◎✨
しみたときの対処法④:1週間以上続くなら歯科へ
1週間ほど様子をみても「まだしみる」という場合は、
もしかすると虫歯・詰め物のトラブル・歯根の炎症などが原因の可能性もあります。
歯石とりのあとにしみた=必ず知覚過敏とは限らないので、
気になるときは遠慮せず歯科で相談しましょう✨
歯科医院では、知覚過敏用の薬剤(しみ止めコート)を塗って
症状を早く落ち着かせることもできます。
それでも「しみる」が怖い人へ
「しみるのがイヤで、歯石とりしたくない…」
そんな声もよく聞きます
ですが、
歯石を取らないままでいるほうが、将来的にもっと痛くなるリスクが高いんです⚡️
しみるのは一時的な反応で、数日で落ち着くことがほとんど
そして何より、歯ぐきが健康を取り戻している証拠✨✨
定期的に歯石をとることで、
歯ぐきもキュッと引き締まって、息もスッキリ!
お口の中の“清潔感”もぐんっとアップします✨
まとめ
歯石とりのあとにしみるのは…
⭐歯石に覆われていた歯の表面が出てきたから
⭐歯ぐきが下がって根っこが見えているから
⭐お掃除中の刺激で神経が一時的に敏感になっているから
そして対処法は…
⭐しみ止め成分入り歯みがき粉を使う
⭐冷たい・酸っぱい・熱いものを控える
⭐やさしく歯を磨いて清潔を保つ
⭐1週間以上続くときは歯医者さんへ✨
歯石とりは、歯を健康に保つための大切なケアです。
一時的なしみはあっても、それを乗り越えたあとは、
お口がすっきりして、笑顔ももっと輝きます✨✨
「しみたけど、やってよかった!」
そう思ってもらえるように、私たち歯科衛生士が全力でサポートします❗
医療法人社団 健晃会
よつば歯科クリニック
📮132-0021
東京都江戸川区中央4-8-4 1F
診療時間
月~土9:30~13:00/14:30~18:30
日9:30~13:00/14:30~17:00
休診日:祝日
お電話はこちら
📞03-5678-4078









